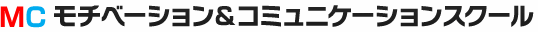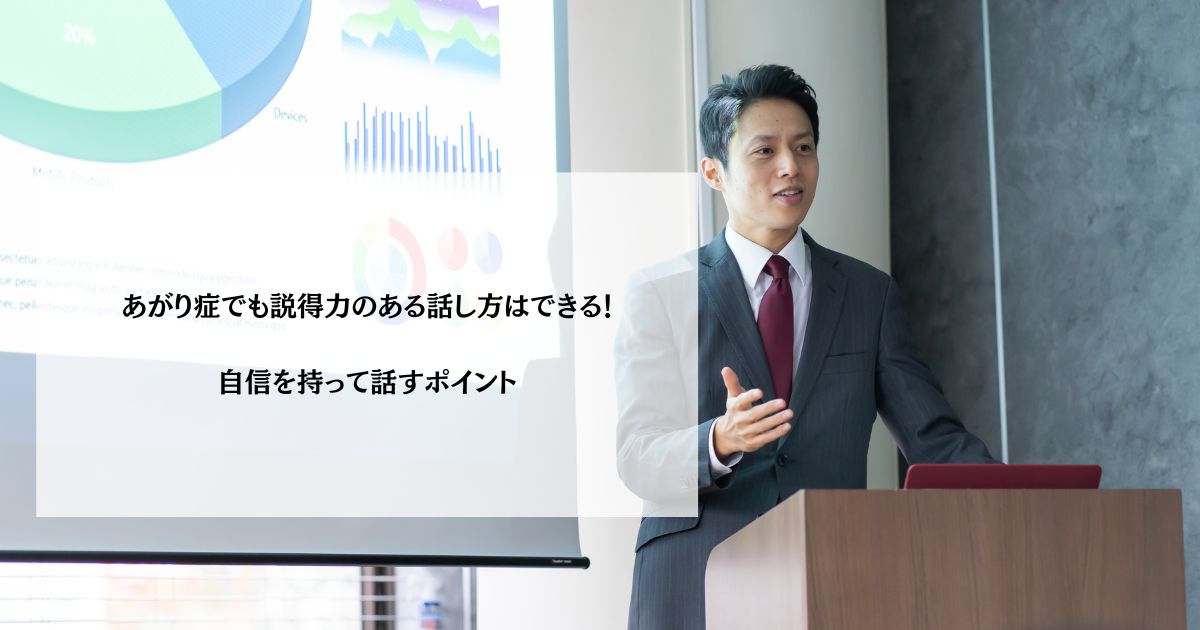
営業やプレゼンの場で「もっと説得力のある話し方を身につけたい」と思っているあがり症の方も少なくありません。
実は、説得力のある話し方は特別な才能ではなく、いくつかのポイントを押さえることで、あがり症の方でも実践しやすくなります。
本記事では、あがり症の方が取り入れやすい「説得力のある話し方」のポイントを分かりやすく解説します。
「あがり症を克服したい」「自信を持って話せるようになりたい」「説得力のある話をしたい」
と思う方は、ぜひ参考にしてください。
はじめまして。桐生 稔(きりゅうみのる)と申します。
私の肩書きや経歴は以下の通りです。
- 株式会社モチベーション&コミュニケーション 代表取締役
- 「伝わる話し方」ビジネススクールを運営
- 全国で年間2,000回セミナーを開催
- 新卒入社後営業成績ドベから心理学を学び全国売り上げ達成率No.1に
- 現在では「伝わる話し方の専門家」として活動し話し方の本を多数出版
Contents
1. 説得力があればあがり症でも緊張が和らぐ理由

話し方や話す内容に説得力があると、あがり症の方でも緊張がやわらぎ、話しやすくなる可能性があります。
これは、説得力のある話し方が緊張の根本原因である「不安」を軽減してくれるためです。
ここでは、説得力が緊張を和らげる理由を解説します。
1-1. 「伝えるべきこと」に集中でき、不安が薄れる
あがり症の方は「うまく話せるか」「失敗したらどうするか」「変に思われないか」など、つい自分自身に意識が向きがちです。
一方で、説得力のある話は構成が明確なので「何を伝えるか」という内容そのものに集中しやすくなります。
意識が自分から相手や話の中身へ移ることで、緊張している自分を意識する余裕が減り、不安もやわらぎます。
さらに、伝えたい内容を簡潔に整理できるため、効率的なプレゼンや説明もしやすくなるでしょう。
1-2. 自信が生まれ堂々と話せるようになる
説得力のある話し方ができるようになると、自信につながります。
自信とは性格や能力から生まれるものだけではなく、小さな成功体験の積み重ねからも自然と育まれます。
説得力のある話は、論理や根拠に基づいているため、「自分の話は筋が通っている」という確信を持ちやすいのです。
この感覚が、声の震えや視線の泳ぎといった、あがり症特有の身体的な反応を抑え、堂々とした態度を後押ししてくれます。
1-3. 質問に対応しやすくなる
会議やプレゼンで怖いのが「想定外の質問」です。
事前に内容を整理し、自分の理解を深めておくと、「なぜそう言えるのか?」「他に考えられる選択肢は?」といった質問を予測でき、答えを用意しやすくなります。
質問を想定しながら話せると、一方的な説明ではなく「対話」として進められるため、落ち着いて対応できるでしょう。
実際に多い質問は、大きく分けて「説明した内容の詳細」「コストパフォーマンス」「人材やリソース」などです。
こうした想定問答を準備しておけば、不意の質問への恐怖がやわらぎ、冷静な質疑応答につながります。
質問への回答のポイントについては、「 【質疑応答】会議・プレゼン後の質問にスムーズに答えるコツ」をぜひ確認してみてください。
2. あがり症の方が説得力のある話し方をする5つのポイント

話し方のコツを押さえれば、あがり症の方でも意識的に説得力のある話ができるようになります。
ここでは実践しやすい5つのポイントをご紹介します。
2-1. 一番伝えたいことを最初に話す
まず相手に伝えたい「結論」を最初に述べましょう。
面接や商談、電話対応など限られた時間で行う場面では、結論から話すことが効果的です。
「結論→理由→事例→再び結論」という流れはPREP法と呼ばれ、説得力ある話し方の代表的なフレームワークです。
例えば、新しいツールの導入提案なら次のようになります。
・結論:業務効率化のため、グループチャットの導入を提案いたします
・理由:グループチャットを導入すると、伝達ミスが減り、社内のやり取りが効率化します
・事例:A部署で試験導入したところ、確認作業が減り、他の業務に使える時間が増えました
・結論:実際に効率化につながっているため、全社導入を検討すべきです
一方で、結論からいわないほうがよいケースもあります。
例としては、新しい顧客に対して詳しい説明が必要なときなどです。
こうしたときは、最初に伝えたいのは説明部分です。
説明や事例を伝えてから、結論を告げることで、新しい顧客でも内容を理解し、結論を受け入れてもらいやすくなります。
説明の順序については「わかりやすく伝えるのが苦手…説明下手を克服する方法は?」もぜひ視聴してみてください。
2-2. 相手が理解できる流れで話す練習をする
説得力を高めるには「相手に理解される流れ」で話すことが大切です。
・内容の定義
・話の構造
・話す順番
この3点を意識して整理すれば、あがり症でも分かりやすく伝えられます。
また、説得力のある話には「要約力」も求められます。
日常の情報を一言でまとめる練習(例:ニュースを一文に要約)を続けると、論理的に整理する力が鍛えられます。
要約する力や話し方のトレーニングについては、下記の記事も参考にしてください。
「説明したいことをひと言でまとめる「サマリーメソッド」!」
2-3. 具体的なデータを用いて話す
根拠を補強するには、数字やデータが効果的です。
例えば「このツールを導入した結果、売上が1,000万円から20%増えて1,200万円になった」といった具体的な数値は、信頼性を一気に高めます。
根拠を示す話し方については「説得力が高い人の話し方!話に根拠を持たせるコツ」も参考になるでしょう。
また、あがり症の方向けのプレゼン成功法について知りたい方は「プレゼンを成功させる話し方の3つのポイント!」もおすすめです。
根拠を持たせる話し方については、「説得力が高い人の話し方!話に根拠を持たせるコツ」もぜひ参考にしてみてください。
また、あがり症の方向けのプレゼンを成功させるポイントについて知りたい方は「プレゼンを成功させる話し方の3つのポイント!失敗しやすい特徴もご紹介」も参考になるでしょう。
2-4. 聞き取りやすい声のトーンや大きさを意識する
どんなに内容が良くても、声が聞き取りにくいと説得力は半減します。
緊張しやすい方は、誰かに聞いてもらう練習が難しい場合もあるでしょう。
そんなときは、自宅や人目につかない場所でできる発声練習がおすすめです。
・舌を数秒間出す
・上の前歯が少し見える口の形で話す
・鼻濁音を意識して発声する
こうしたトレーニングは、通る声を出すのに役立ちます。
それぞれの詳しい練習方法は「声がこもる、モゴモゴ話してしまう方必見!通る声を出す意外な方法」をぜひチェックしてみてください。
2-5. 専門用語を使いすぎない
専門用語を多用すると、相手が理解できず、説得力を失ってしまうことがあります。
できるだけ分かりやすい言葉に置き換えることで、相手の理解が深まり、印象も良くなります。
資料を使うときは「資料をなぞる」だけではなく、自分の言葉で補足する意識を持ちましょう。
3. まとめ
説得力のある話し方は、あがり症の方でも落ち着いて話しやすくなり、話すときの自信にもつながります。
本記事でご紹介したポイントは、少し意識すれば実践しやすい内容です。
実践できる内容から少しずつ試し、できることを増やしていけば成功体験の積み重ねになります。
もし「あがり症でも堂々と話したい」「緊張しない話し方を知りたい」という方は、「あがり症を克服するセミナー」もおすすめです。
セミナーの詳細は、以下の案内をご覧ください。